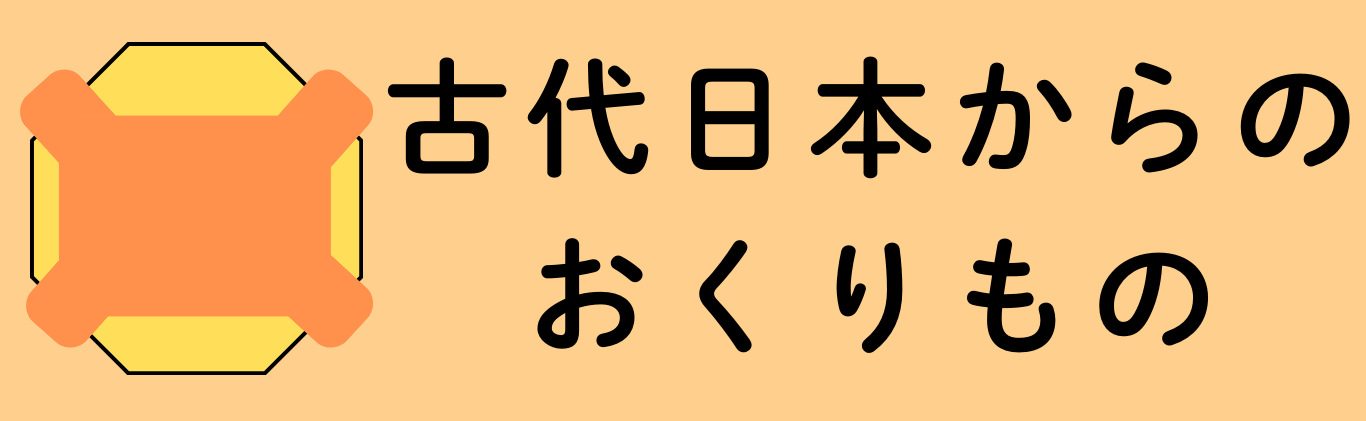なぜ吉野ヶ里遺跡は価値がある?
日本一有名と言っても過言ではない弥生遺跡が、この吉野ヶ里遺跡でしょう。




この遺跡の価値を簡潔に並べると、以下の通りです。
- 弥生時代最大級の集落跡だから
- 弥生時代当時の生活・社会を伝える豊富な文化財が出土しているから
- 小さな「ムラ」から「クニ」になるまでの変遷がわかる遺跡だから
- 日本の城の原点とも言える場所だから
1~3は、そのままの意味ですが、4は、少し様相が違いますね。 要は、日本の城で見られる防御機能が備わった最古の遺跡と言う訳です。


日本の城で見られる防御機能の最古の例が数多く残っています。
そして、この遺跡を語る上で欠かせないのが、邪馬台国との関わりでしょう!そのことについても話していきましょう!
説1:ここは邪馬台国の都?
吉野ヶ里遺跡は発見されて以降、規模や出土品からも、『魏志倭人伝』に登場する邪馬台国の都ではないかと言われ続けています。
吉野ヶ里遺跡が栄えたのは紀元前5世紀から紀元後3世紀までの、およそ800年間にも及びます。 『魏志倭人伝』の時期は紀元後3世紀と考えれば、時代背景は重なっています。 他にも、『魏志倭人伝』に書かれた大きな王国の姿がはっきり残っているだけでなく、 書かれている内容とリンクするような出土品(棺など)も見つかっています。 これらの証拠が、邪馬台国の都ではないかと言われる理由ですね~。
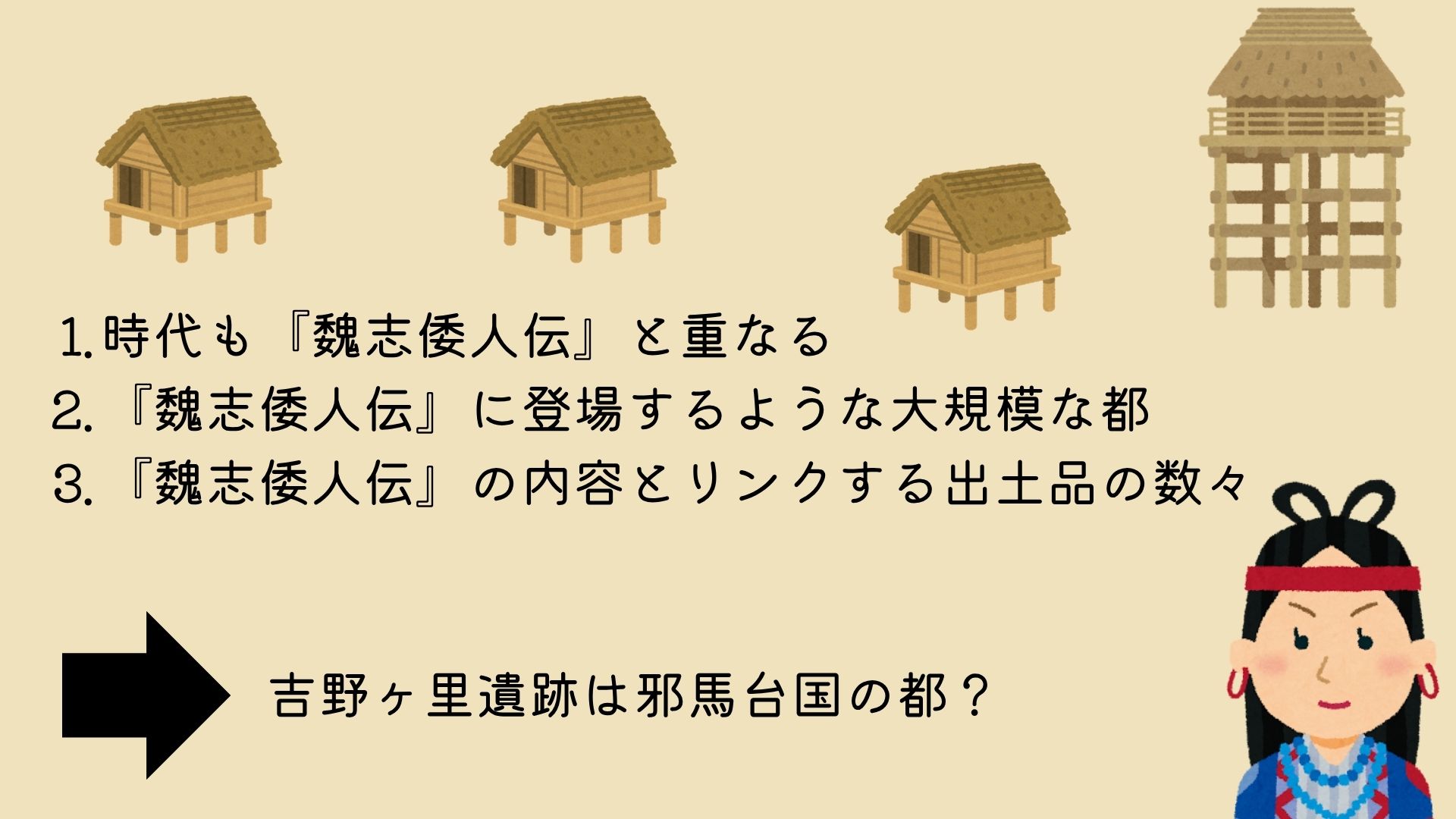
説2:ここは最古の日本人の都
ただ、『古事記』や『日本書紀』といった古書に書かれている内容を読んでいくと、 別の王様の都だった可能性が出てくるんです!
『日本書紀』では、吉野ヶ里遺跡が位置する地域周辺には、「筑志米多国」が存在したと書かれています。 一方、中国の『後漢書』には、倭の面土国の帥升が、後漢に使者を派遣してきたと書かれています。 突然出てきた帥升という人物。誰?という話ですよね。 実はこの人物、卑弥呼の100年以上前の西暦107年に中国に使者を派遣しているだけでなく、記録に残る最古の日本人でもあるんです! 面土国については、どう読むのかはわかっていませんが、少なくとも[m]と[t]の音が使われる地名だったとされています。
そう、米多と面土って、言葉の響きが似ていますよね。 そして、中国での年代と吉野ヶ里遺跡が栄えた時代も重なっています。 つまり、邪馬台国ではなく、より古い記述が残る面土国の都だったかもしれなんです!
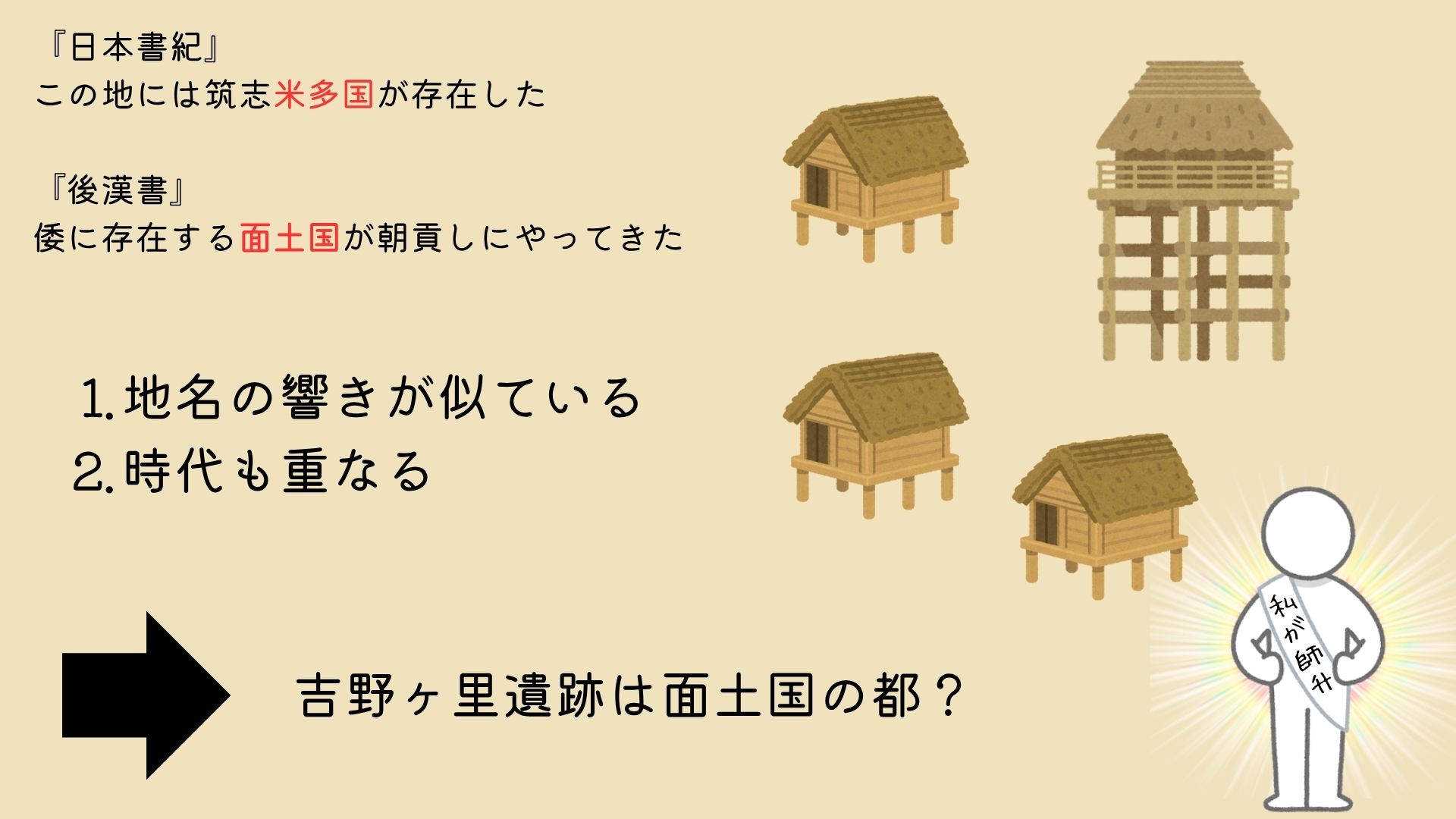
いずれにせよ、どちらが正しい、どちらが間違っているという話ではなく、 遺跡1つでここまでの説が浮上するという事自体がスゴイことではないでしょうか。 多くの人が古代史に関心を持つきっかけを作り、様々な考察を行うことが出来ることに、 吉野ヶ里遺跡の価値があるのかもしれませんね。