師升って誰?
このページでは師升という人物について深掘りしたいと思います!
まず、この師升という人物がどんな功績をしたかというと、 記録に残る中で最も古い時代に、日本から中国に朝貢を行った人物です! 中国では後漢の時代に当たる西暦107年に、その朝貢が行われたと『後漢書』に残っており、 これは実に卑弥呼の100年以上前の出来事です!
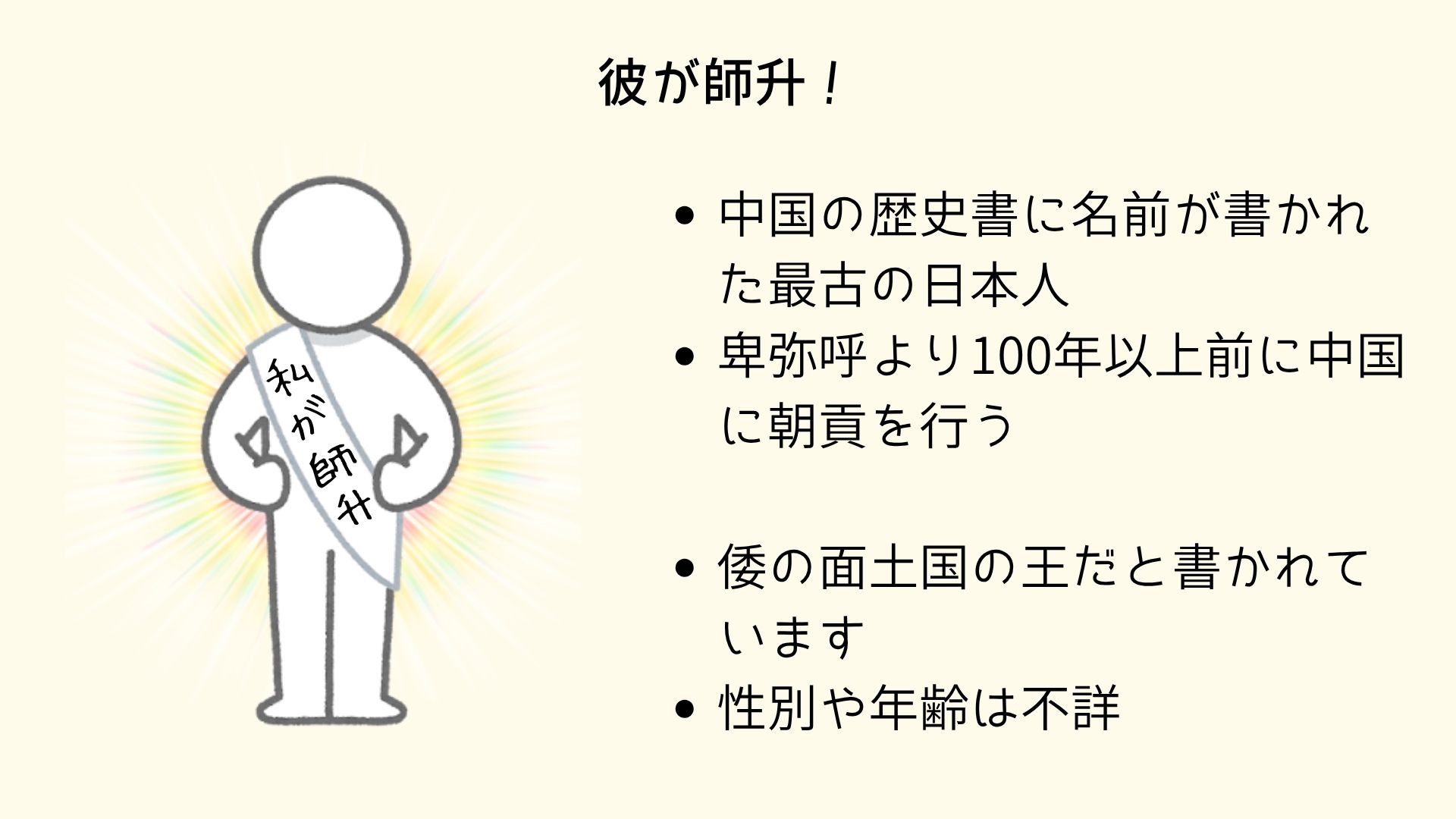
本来ならば卑弥呼より有名でもおかしくない人物なのですが、いかんせん地味ですよね~。
ただ、このページではこの地味な人物への印象がガラッと変わることになります!
まず第一に、師升については性別も人柄もわからないので、 個人的な特徴については深掘りできません。
そこで、師升が王だった倭・面土国の場所を可能な限りで比定していきたいと思います。
地名に残る面土国の痕跡
あまり聞きなれない地名ですよね。面土国って。 これが日本のどこなのか、結論を先に言っちゃいましょう!
師升が王だったメト国とは、吉野ヶ里遺跡です!多分、、。
.jpg)
理由:この地域の地名
まず吉野ヶ里遺跡があるのは、佐賀県神埼市と、神崎郡吉野ヶ里町にまたがる地域です。 これだけではさっぱりですよね。 そこで、この時代と近い時代の記述から判断してみましょう! このサイトでの判断で3世紀末のものだと思われる記述では、 吉野ヶ里遺跡がある肥前東部の地域は「筑志米多国」だったと書かれています。
この「筑志米多国」は、「ちくしのめたこく」と読みます! 似てますよね?「メト」と「メタ」という響き! まあ、前半部分の「ちくしの」は普通に考えれば、あまり気にしなくてもいいと思います。作成者は。
ちなみにこの3世紀末と思われる記述と言うのが、『古事記』と『日本書紀』などで見られる国造のものです。 国造とは、今でいう知事のような、江戸時代でいう大名のようなものと考えてください。 その国造に関する記述の中で、当時の国名も登場するという訳です。
この国造に関する記述の中で、「メ」の音がある国は、「筑志米多国」のみでした!
つまり、現段階の情報量だと、「面土国」=「筑志米多国」=「吉野ヶ里遺跡」と充分に考えられるという訳です!
そう、吉野ヶ里遺跡は卑弥呼よりも100年以上前に、中国に朝貢した師升の王国跡だったんです!
この時代の吉野ヶ里遺跡
吉野ヶ里遺跡は弥生時代前期から存在する遺跡ですが、 この師升が活躍した橿原時代(弥生時代後期前半)に最盛期を迎えます。 集落を囲む環濠は日本最大級で、建物も大型化するなど、国の王都と呼ぶにふさわしい造りでした。 ちなみに、現在の吉野ヶ里遺跡公園で復元している主な時代は、この時代の遺構です。
.jpg)
この時代は大和で天皇家が成立したことで、各地で競うように勢力拡大が図られました。 そして、同じ九州の奴国(福岡県)の王が金印を受け取った時代でもあります。
そんな勢力拡大をしなければならない時代にメト国は、中国に朝貢することで勢力拡大を図ったようです。 その国の王都の全体像を見ることが出来るのが吉野ヶ里遺跡という訳です。 どうです?少し古代史がリアルに感じてきたでしょう?
作成者としては、古代日本と言えば卑弥呼!という考えでも面白いですが、 卑弥呼の100年前に中国に朝貢した人物の王都が吉野ヶ里遺跡だったかもという考えだと、 古代日本の世界が広がり、より面白くなるのではないかな~と思ったり思わなかったり、、。
そしてこの後、日本は倭国大乱を迎えますが、大乱が終わるとメト国の王都である吉野ヶ里遺跡は見捨てられることになります。 大乱中に何があったのか、、。
一方の肥前北部の松羅国は、倭国大乱を経て邪馬台国の勢力下に入ることになります。 こちらもいったい何があったのか、本当にミステリー。
